いつもお弁当を一つだけ買って帰るお客さん。10年後の再会で知ったこと。
「わたしは げんきで くらしています。おげんきで…」
手紙にはベトナム語で長文が書かれていたが、最後の文章だけは平仮名で書かれていた。
長文の内容を理解することは出来なかったが、その手紙には俺への感謝の気持ちが綴られていることは何となくわかった。
手紙の余白には絵も描かれていて、彼女の気持ちが伝わってくるような絵だった。
彼女は留学生として来日し、学校で学ぶ傍ら、俺が店長として働くコンビニでアルバイトをしていたのだ。アルバイトとしては数年程、働いてくれただろうか、留学が終わると、彼女は母国のベトナムへ帰国していった。今では、彼女のようにコンビニで働く来日外国人も多く、俺はこれまで多くの国の人たちと仕事を通して交流を続け来た。
彼女のように、帰国してからわざわざ手紙を送ってくれる人も多く、そんな気遣いに恐縮してしまうことが多いのだが、それはきっと俺が職場の外国人に対して、公私ともに親切にすることを心掛けてきたからなのかもしれない。なぜ、そうするようになったかは、ある人の影響がそこにはあった。
高校1年の頃、俺はアルバイトを始めた。きっかけは、中学からの友人がバイト募集の広告を見て、俺を誘ってきたからだ。そこまでバイトをする気持ちもなかったのだが、その頃、夢中になっていたバンド活動に使う新しいギターの購入資金にしようと、その誘いに乗った。
アルバイト先はコンビニだった。二人とも無事に面接に通ったが、予想してなかったのは、二人のバイトシフトはバラバラだったことだ。
友達と一緒なら気分的に楽だなと甘い考えを見透かされるように、二人とも曜日はバラバラにされ、俺は得体の知れない年上の高校生と働かなければならなかったのだ。
元来、人見知りの性格なため、得体の知れない、同じ中学出身でもなければ、同じ高校でもない、年上の人間と働くのはキツイと思っていたが、その先輩は気さくに話しかけてくれて、接しやすく、仕事も丁寧に教えてくれてすぐに慣れていった。
それでも、初めの頃は、覚える仕事も多く、緊張もあって接客もガチガチな感じであったが、慣れてくると、どんなお客さんが店に来てるのかを覚えるようになっていた。
そのコンビニは駅前にあったので、電車が到着すると一気に人がなだれ込んでくるような感じであった。
しかも、俺がバイトをしている時間は夕方から夜にかけてなので、職場帰りのお客さんがかなりの数で来店してくるのだ。時にはレジに行列ができる事もあり、晩御飯を買って帰る人のプレッシャーはかなりのものがあった。
来店するお客さんには常連のような人もいて、毎日のように同じものを買って帰ったり、晩御飯であろう弁当をローテーションで買って帰るお客さんもいた。
そんなお客さんの中で、俺が気になる人がいた。
そのお客さんもいつも決まった時間帯に来店し、お弁当を一つだけ買って帰っていく人だった。
年齢は50代くらいの男性で、毎日ひとつだけお弁当を買って帰ることから、独身の人なのかなと思っていた。そのお客さんの事が気になったのは、レジが行列になろうが、店員であるこちら側がモタモタしようが、嫌な顔一つ見せないからだった。
お客さんの中には、俺が学生のバイトなのか随分と横柄な態度をしたり、あえて無理な要求をしてくるような変わった客もいたりした。
逆に、年齢的にも未熟であり、バイトであることを良いことに、機嫌が悪い時は俺の方がお客さんに対して失礼な態度を取るような事もあったが、そんな時でも、そのお客さんは嫌な顔一つ見せることはなかったのだ。むしろ、そんな時は、若い俺に温かい目で見てくれるような、そんな印象さえ覚えた。
それから、俺が高校を卒業するまでの間、そのお客さんとは会話こそないが、顔を合わせることが続いた…。
俺は高校を卒業と同時にそのコンビニのバイトを辞め、進学先の学寮に移り住んだ。
たまには地元に帰ってくる事もあったが、そのコンビニにはあえて近づかないようにしていた。
というのも、自分がバイトをしていた所に客として顔を出すのもなんだが照れくさいというか、残っている従業員に客だからと言って頭を下げられるのも嫌だなと思っていたからだ。
そんな事もあり、そのコンビニを利用するのは俺が社会人になり、実家に戻ってきてからになる。
社会人になった俺がある日、会社へ出勤する途中のことだった。
その日は、新人研修でいつもよりも朝早く自宅を出て、駅で電車を待っていた。
電車がまもなく駅に着こうかとする頃、階段から一人の壮年が上がって来た。
俺はすぐに「あのお客さん」であることが分かった。あれから4年が過ぎていたが、見た目を変わっておらず、特徴であった片方の足を引きずる姿で間違いないと思ったのだ。
俺は久しぶりに再会するような気持ちで「あのお客さん」を見ていたが、こちらには気づかず、電車に乗り込んでいった。あいにく乗った車両は別であったので、その後にどこで降りて行ったのかも分からないが、俺は会社に着くまでの間も気になり、高校生の頃には感じなかった考えを巡らしていた。
「あのお客さんはどんな仕事をしているのだろうか」
「あのお客さんはなぜ独り身なのだろうか」
「なぜ、足を悪くしたのだろうか」
「まだ、あのコンビニ使っているのだろうか」
「なぜ、あんな穏やかな目で人を見れるのだろうか」
そんな、取り留めもない事を考えていた。
というのも、大人社会に入った俺は、この人間社会で繰り広げられる大人の戦いの中で、心から信用ができる大人はいないと悟りはじめていたのだ。
弱肉強食の社会の中で、人を見る目は今までと違うようになっていた。そして、相手がどんな目をしているのかを観察するようにもなっていた。皆、心をすり減らして生きているのだと思っていた。だから、レジに行列ができたり、店員がモタモタすれば嫌な顔をするのも当たり前なんだなと昔の事を振り返ることもあった。だから、余計に「あのお客さん」の気遣ってくれるような目が不思議で仕方なかった。
その後、通勤する電車の時間が違っていたのだろう、「あのお客さん」を見かけることはなかった。
俺も仕事に追われるような毎日で、そんな事も忘れるようになっていた。
それから10年の月日が流れた。
俺は職場でのパワハラが原因で精神疾患を患い、休職や復職を繰り返したのち、半ば強引に会社から退職届を書くように迫られ、泣く泣く10年も勤めた会社を退職しなければならなかった。途方に暮れ、何もかもが嫌になり、自暴自棄になりつつあった。
それでも、生きて行くにはなんとかしなければならない。俺は失業届を出すため、ハローワークへ訪れた。再就職をどうすれば良いか、相談窓口でも話を聞いたが、病気の事や年齢的にも、再就職先のハードルは下げないといけないことが分かった。現実を見せつけられ、俺の心はしんどくなる一方だった。
ハローワークの帰り道、肩を落としうつむき加減で歩いている俺がふと顔を上げると、目に飛び込んできたのは、「あのお客さん」だった。
思わず、「あ!」と声を出してしまったが、同時にその変わり果てた姿に驚ろきを隠せなかった。
その頃には60代になっていただろうが、見た目はそれ以上に老けていた。髪もボサボサであの頃にはなかった髭を伸ばしていて、駅の掲示板を見ながら、独り言を何度もつぶやくその姿は、病を抱えているようだった。
声をかけようにも何て言っていいかも分からない。しばらく、様子を見ていると、仲間らしき人がやってきて「あのお客さん」に声をかけた。持ち物や恰好から、どうやら二人ともホームレスになっている事は理解できる。俺は何とも言えない気持ちになり、後を追いかけ二人に声をかけた。
「あの、すいません…」
声をかけた理由を説明すると、「あのお客さん」の仲間が俺にこう言った。
「この人はもう昔の記憶はないよ…」
俺は咄嗟に、
「何か買ってくるんで待っててください」
と言って近くのコンビニに走った。おにぎりや惣菜を買い、急いで戻ってくると二人は待っていてくれた。買ったものを渡すと二人は喜び、近くの公園へ誘ってくれた。
公園のベンチに座りながら二人が食事をしている横で俺は自分の事を話はじめた。すると、怪しい物ではないことを分かってくれたのか、仲間の人が「あのお客さん」について何があったのかを教えてくれた。
「あのお客さん」はリストラで仕事を失い、2年程前からこの付近でホームレスをしていて、1年前に病気の影響か過去の記憶を失っていったのだ。
仕事を失った後も諦めずに毎日のようにハローワークに通っていたが、再就職はできず、やがてこの場所に住むようになったようだ。そして、まだ記憶がある頃に過去の自分の事も話していたらしい。
「あのお客さん」は自分が運転する車で交通事故を起こし、同乗していた奥さんと子供を亡くしていた。
片方の足を引きずっていたのは、その時の事故が原因のようだった。
仲間の人が話している最中に、「あのお客さん」の表情を覗いたが、記憶だけが失われているだけではないと思った。どこか、呆然と聞いているような所もあり、全てが他人の話と理解しているようだった。
俺は話を聞き終わると、感謝の気持ちを伝え、その場を後にした。
「あのお客さん」が見せていた、あの温かい目は、亡くなった息子さんと俺を重ねていたのかもしれない。どんなにつらい出来事があっても、立ち上がり、懸命に生きようとしていたのだろう。不自由になった足を引きずり、そのハンディキャップがあっても、この社会で戦っていたのだ。
贅沢な暮らしをするわけでもなく、誰かに迷惑をかけるわけでもなく、ただ、命が尽きるその日まで生きようとし、仕事を失っても最後まで諦めようとしなかった。自分の記憶を失うその日まで。
俺はその再会を機に転職先をコンビニと決め、何とか正社員にもなり、やがて店長にまでなる事ができた。
そして、「あのお客さん」が教えてくれた生き方というものを一番に大切にして、どんなお客さんでも、共に働くどんなアルバイトの人でも、同じように大切にするようになっていった。

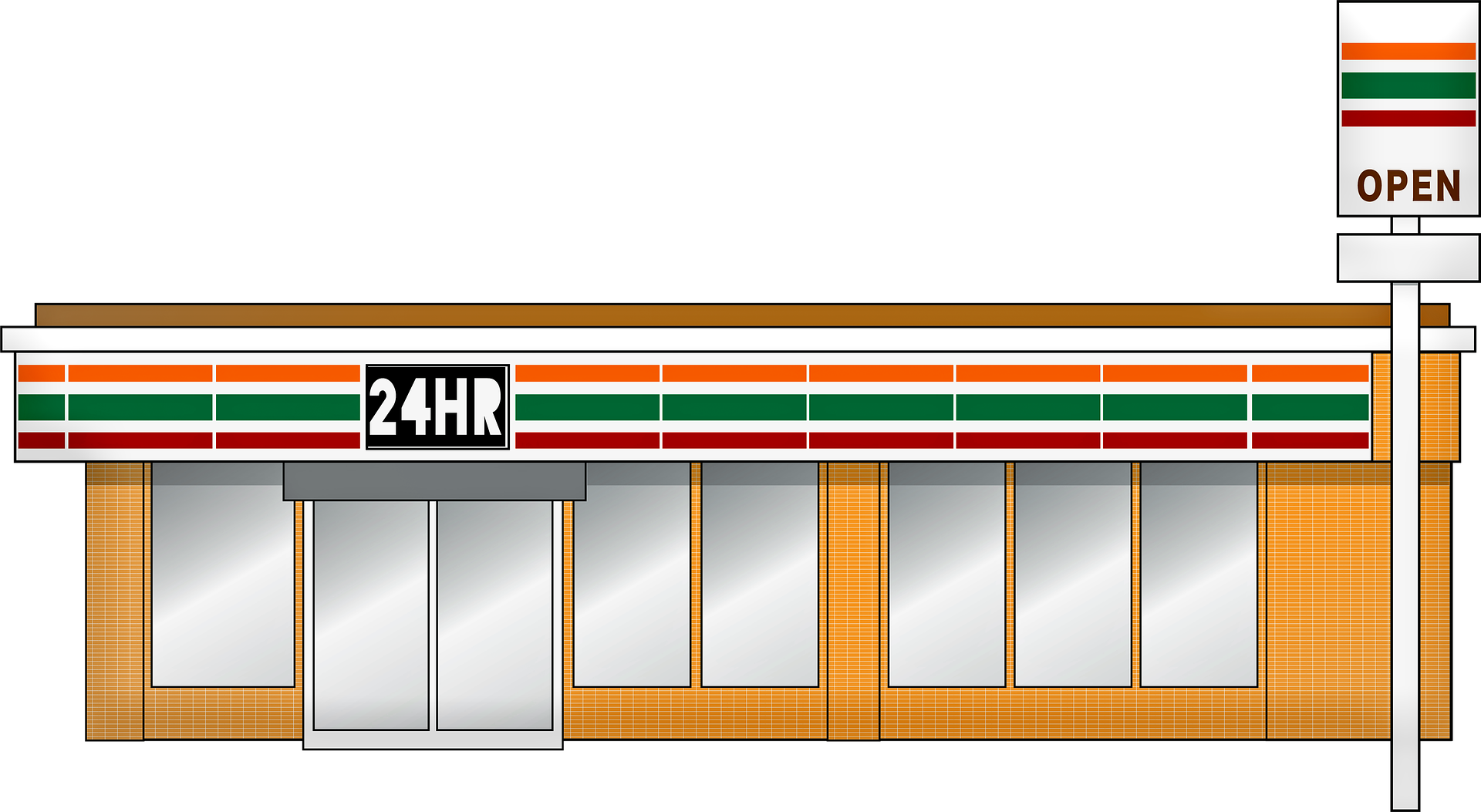


コメント