小学校3年生の時に遠い地へ引っ越した親友 30年後にその理由を知った
小学校3年生の時に親友が遠い地へ引っ越した。
友達は山君という名前で、俺とは違い坊ちゃん刈りの勉強のできる賢い友達だった。
笑いのツボが同じだったのか、いつしか意気投合して遊ぶようになり、親友と呼べる仲になった。
二人で今思えば何でもない事で笑っていた事を思い出す。
スポーツマンではない山君だったが、野球が好きで他の友達を誘っては、カラーボールとカラーバットで野球をやったりしていた。山君が左投げであったことから、当時の友達の中では珍しい存在で、
山君がボールを投げる姿を皆で面白がる気持ちと、羨ましがる気持ちで見ていた。
二人で探検という名の遊びをよくしていて、行き先で野良猫がいると、その野良猫に餌をあげるため、その資金集めに奔走した。
資金の集め方は子供らしく、自動販売機の下に落ちているお金を探すことと、コーラの瓶を探し出し、酒屋に持っていき現金に換えてもらう方法だった。
数百円のお金を手にすると、コンビニに行き猫の餌を購入した。小銭が余る時はスーパーで格安で売っているプラスチックの桶を購入し、自宅でお湯を入れて野良猫の湯舟にするという追加ミッションを加えるものだった。
野良猫としては餌についてはありがたかったのだろうが、湯舟は勘弁という表情をしており、二人で逃げる野良猫を追いかけまわし笑っていた。最終的に段ボールを拾ってきて、野良猫の家を作り、中に入れて帰るのだが、次の日に見に行くと、もうそこには野良猫の存在はなく、二人で肩を落としていた。
学校が終われば毎日のように二人で遊びに出かけたが、山君の家は門限が厳しく、夕焼けチャイムが鳴ると山君は走って家に帰っていった。
そんな山君がある日、学校で俺にこう話しかけてきた。
「俺、引っ越すことになったんだ…」
小学校3年生ながら、その意味を理解し、その時の衝撃は大きかった事を覚えている。
学校のクラスでも担任の先生から山君が引っ越すという話があった。そして、クラスの皆でお別れの文集を作ろうという事になり、それぞれが山君への作文を書いた。
担任の先生から渡された作文用紙は小さく、そこには書ききれない思いがあったが、俺はあえて作文用紙の半分だけ文章を書き、半分の余白に絵を描いた。
それは山君が左投げで投球する絵だった。それを出来る限りの時間をかけて描いた。
最後に二人で遊んだ時、いつもと同じように夕焼けチャイムが鳴っていたが、俺は大声を出して、それが聞こえない様にしよとした。そんな事をやっても夕焼けチャイムがかき消されるわけでもなかったが、小学校3年生としての最大の抵抗だった。
隣を見ると、山君も大声を出して夕焼けチャイムに抵抗していた。そして、二人で笑った。
それから1カ月も経たないうちに山君は引っ越した。
担任の先生から教室の前に呼ばれた山君がクラスの皆に最後のお別れの挨拶をしている、その時の場面は今でもはっきり覚えている。眼鏡をとり、涙を拭く山君の姿にクラスの皆は静まりかえっていた。
次の日から何事もなかったように授業が始まり、俺はといえば、自然に他の友達と遊ぶようになっていた。友達と野球をやり、探検をして野良猫が見つければ、いつものように餌をあげるという変わりのない遊び。ただ、そこには左投の友達がいなくなったという、他の友達皆が共通する寂しさがあった。
その年が明け、元旦の日に思いがけない出来事があった。
山君から年賀状が届いたのだ。俺は山君の引っ越す住所を聞いていなかったので、年賀状を送っていなかったのだが、向こうから送ってくれたのだ。それは手の込んだ年賀状で、色んなメッセージが散りばめられていて、山君の近況が凄くよく分かるものだった。
それからは、年に一度、年賀状を通してお互いの近況を報告するようなやり取りが続いた。
遠い地でも元気に過ごしている。新しい友達も出来て楽しく暮らしている。野球も相変わらずやっている。こちらでは見られないような風景の絵を描いてくる事もあった。
お互いがそれぞれの場所で成長しながら、年に一度、それぞれが成長した姿を一枚の年賀状に込めるというやり取りは、親友の存在のありがたさを感じるものだった。
俺は冬休みが明けると、学校で山君の近況を皆に話し、その瞬間は皆が興味津々で話を聞くというのが恒例となっていた。
その状況が変わったのは中学2年の時だった。
その年の元旦には山君からの年賀状は届かず、俺が送った年賀状も宛先不明で送り返されてきたのだ。その時は心配になり、またどこかに引っ越したのだろうか、何かあったのだろうかと考えていたが、思春期の感情は複雑なもので、それはいつしか記憶から薄れていくものだった。
その後、俺は大学を卒業すると、輸入販売の会社に入社し営業職に就いた。来る日も来る日も、営業先をまわり、足を棒にし、靴底を減らすという毎日。
多忙な毎日だったが、子供の頃に遊んだ探検のようで、生きがいを感じ仕事にも慣れていった。ある時、大型スーパーへ営業に行くと、仕入担当者から一つの相談を受けた。
「斬新なポップデザインを作ってくれませんか?」
ポップとはスーパーの売り場にあるような、値段や商品が書かれた説明書きのことだ。
その相談を受けた俺は、要望に応えられるようなポップデザインを探すため、インターネットで様々な業者を調べていた。その中で、検索一覧の上位ではないが、ひときわ目立つホームページを見つけた。ホームページのトップページが目を引くものであるから、きっとこの業者なら何かあるだろうと、詳しい内容を見ていった。
その業者は少人数の会社ながらもポップデザインを専門にしていて、長くその業に携わっているようだった。そして、その会社の代表者の名前を目にして、俺はマウスを動かす手が止まった。
その代表者は山君だったのだ。写真も載っていて、その顔は小学3年生の頃とは別人ではあったが、面影はのこっていた。こんな形で幼い頃の記憶を蘇らせるとは思わなかった。
動揺する自分を感じながら、本当に山君であるかを答え合わせするかのように、そのホームページをくまなく見ていった。すると、その中に、代表者の経歴とエピソードが載せられたページがあった。
それを見る限り、やはり、小学校3年生の時に引っ越していった親友の山君で間違いなかった。それだけはなく、俺はそこから30年という歳月で知らなかった事実、いや、自分の記憶から消し去っていた事実を知ることになったのだ。
山君は現在、両親の故郷である地域で仕事をしていた。数年前に起きた台風で甚大な被害を受けた、両親の故郷の復興のために、その地に移転して今の仕事を営んでいるという事だった。
それまで、ポップデザインに関わる仕事をしてきて、独立した形で会社を興したのだ。そして、山君は幼少期の思い出や出来事、この仕事に携わるきっかけなども載せられていて、そこには、小学校3年生の時に生まれ育った地を離れ、引っ越しをしたエピソードも書かれていた。
山君は小学校3年生の時に友達との関係に悩み、学校に行きたくないという気持ちを度々、両親に訴えていることが分かった。両親は一人息子の山君の事を思い、他の地域に転向することが子供のためと決断し、引っ越しすることになったという事だった。
俺はその事実を知り、驚きを隠せなかった。いつも、二人で楽しく遊んでいた、あの山君が友達との関係で悩んでいる風には思えなかったからだ。その続きのエピソードはこうだった。
関係に悩んだ友達とは毎日のように遊んでいた。だが、その友達は、よく言えば強引で悪く言えば自己中心的で、自分のやりたい事を受け入れてくれない友達と一緒にいる事がいつしか苦痛になっていた。
ある時、同じクラスの女子が遊びに加わった時、友達はいつもと違う態度を表し、いい恰好をする友達に強い嫌悪感を抱いたが、友達に自分の感情を率直に伝えられない事に自分自身が凄く惨めに思えてしかたなかった。自分がその友達よりも下の立場にいるという気持ちと、同い年の友達に負けているという敗北感がとても嫌で両親に訴えるきっかけになった。
引っ越しが決まり、気持ちが楽になったが、その友達は自分がもう遊びたくないという感情に気づいていないらしく、その後も遊びを誘ってきては、いつものように強引に自分がやりたい事を付き合わせるという毎日だった。
だが、自分が転向する前日、最後に二人で遊んでいる時、帰宅する報せの夕焼けチャイムが鳴ると、友達は大声をあげて、その音が自分に聴こえないようにしていた。その姿を見た時、嫌いになっていた友達に対して、なぜか許せる感情が芽生えた。
生まれ育った地を引っ越した後、その友達とは年に一度年賀状でやり取りをしたが、年賀状を出そうと思ったのは、二人で遊んだ最後の日の出来事とクラスの皆が書いてくれたお別れの作文の中に、その友達が描いてくれた絵によって引っ越すことが寂しいという気持ちになったからだ。
その友達との年賀状の交流が途絶えたのは中学2年の時、親の事情で夜逃げ同然で急な転居を余儀なくされ、その際に友達の住所なども分からなくなった。転居届なども出せる状況ではなかった為、その友達からの年賀状が自分の所に届く事もなくなった。
後に自分の家庭が夜逃げをする状況にまで至ったきっかけが、引っ越しから始まった事を知った時に、自分のわがままが両親を追い込んだのではないか。自分が嫌いになった友達は、本当は親友だと呼べる存在だったのではないか。歳を重ねるごとにその事は頭の片隅に後悔として刻まれていった。
ポップデザインの仕事についたのは、その友達が作文と年賀状に描いていた、絵と短い文章で相手の心に訴えかける形を仕事にしてみたかったのと、その仕事をしていれば、いつの日か必ず、自分がデザインしたものをその友達が目にすると思ったからだ。
30年という月日が経っていたが、そのエピソードを読み、俺は山君との思い出が昨日の事に蘇っていた。
俺は自分勝手に親友との別れを記憶の中で綺麗に塗り替えていたのか、それとも、都合の良いように自分の不都合を消し去ってしまったのか困惑した。
だが、山君は色んな事を乗り越えて立派に生き、俺との思い出を生きる糧にしてくれている。やはり親友という存在で間違いなかったのだ。
これから起こるであろう再会はきっと二人の新たな探検の始まりであるはずだ。
俺は問合せフォームを開くと、気持ちの高ぶるまま、思いのたけを綴り、そして送信ボタンを押すのであった



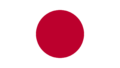
コメント